2024/06/06 21:38

当たり前のようで、そうでない名前。
某化粧品会社のデザインがとても好きなわたしにとって、椿に関わるもののブランディングを行うのは結構むつかしかった。好きなデザインに引っ張られることなく、このブランドらしさを正しく追求するのだと、何回考えを改めたことか。そして、自分のくらす土地のデザインをすることの楽しさを改めて感じたのも、木春のブランドを通してだった。

名前から決めるお仕事はこれが初で、はじめてのことに取り掛かるときはもっぱら本頼みでなのでネーミングの本を何冊か読むことからこのお仕事がはじまった。分析、名前へのアプローチ、作成、検証。本に出てきたすべてのアプローチのパターンを試し、そこから選別するためのいくつかの条件を定めた。「椿」の漢字を分解してどスレートに「木春」。読み方も数パターン考え、定めたいくつかの条件のひとつ、みんなから愛されることを念頭に、名前を呼ぶような、優しい気持ちになれる気がする「こはる」に決まった。観光客をターゲットにするときには特に「分かりやすさ・覚えやすさ」が必要で、それはこのあとつくる商品パッケージなどのデザインにも反映されていく。
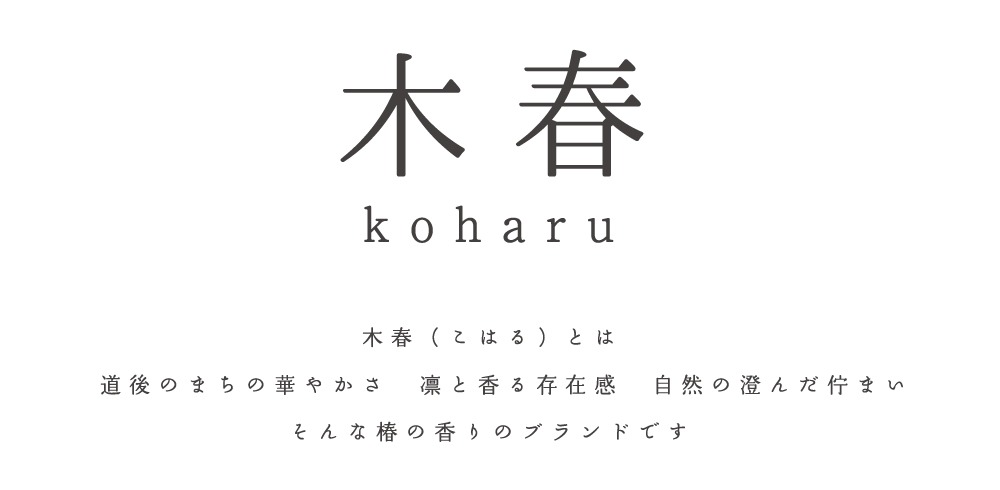
このブランドは、まちづくりを実践的に学ぶ市民参加型の学習プログラム・アーバンデザインスクール松山の取り組みのなかでうまれた、松山市の市花である「椿」を、愛媛のブランドにできないかという「椿のおもてなしプロジェクト」からはじまり、実際に商業展開するにあたりブランディングをしたいとお話いただいたもの。愛媛県の道後地区をはじめ市内の至る所で見ることができる椿。椿を県木・市花に定める自治体は多数あり、独自の商品を販売している自治体もあるが「香り」によるまちづくりはあまり着目されておらず、このプロジェクトでは香りが持つ「記憶を呼び覚ます力」(プルースト効果)の人の感情・記憶と深く結びつき、過去のシチュエーションや印象と共に記憶に残ることを、観光の思い出のひとつとして活かせないか、とスクールで活動してきた内容や今後の構想を伺った。
ブランディングデザインするにあたり1点気掛かりなことが。実は「椿」の花自体には香りがないのだ。一瞬、どう表現したらよいだろう?と思った。しかしこのプロジェクトは「椿」をブランド化したいわけではなく愛媛・松山のまちを「椿」というモチーフでブランド化したいわけで、むしろ、香りを「花自体の香り」に影響されずコントロールできるというのはメリットだと感じた。ターゲットは主に女性、観光客に向けて、椿のもつ凜とした印象や道後のまちの華やかさを感じてもらえるような、すこし大人びていながらも愛されるブランドにしようと方向性が定まり、コミュニケーションをとりながら「木春」という名前、ロゴデザイン、パッケージなどをかたちづくっていった。
明らかに「椿」とわかるベーシックさ、可愛いけれど可愛らしすぎない印象、お店にならんだときの視認性、価格感と見た目のバランス。今では当たり前のように思える名前もビジュアルも、この愛媛・道後の地で、思いが詰まってうまれてきたブランドだからできていったものである。


年々いろんなアイテムがつくられ、当初から椿だけでなく「愛媛各地の香り」も構想があったそうで、リリースに向け調香されたものを吟味しているところにもお伺いしたり、「愛媛を旅する香り」というコンセプトのもと4種の香りのデザインや店舗のデザインをお手伝いさせていただいたりして、一緒にいて、プロジェクト自体が楽しくて仕方ないというようすにとても感銘を受けた。その思いとワクワクが、いまもずっと続いて世界に広まっている。